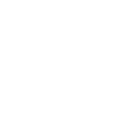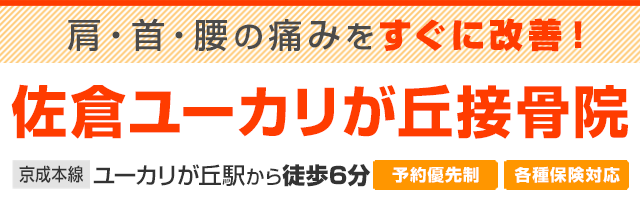オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

部活中にスパイク練習をしていると、膝がだんだん痛くなってくる。その後も動いているときに、違和感を感じる
サッカーをしていると、ドリブル中に膝に違和感を覚える。練習はほぼ毎日あり、ストレッチをする時間が少ない
体育の時間に長距離を走った後、膝に違和感があった。
クラブでバスケットボールをやっていて膝に違和感があり、何もしていない時でも痛むようになった
学生の頃からランニングをしていて膝に違和感がある程度だったが大人になり、膝に違和感から痛みに変わった
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッド(オスグッド病)とは、膝の下の骨が盛り上がっている部分、脛骨粗面(けいこつそめん)と呼ばれる“すね”の骨に痛みが生じる病気です。医学的には「オスグッド・シュラッター病」と呼ばれています。
この症状は一般的に小学生から中学生の成長期にあたる男児に多く見られます。 子どもの骨には、成長骨端線という骨が成長する部分があります。成長期に脛骨粗面の骨端軟骨という、骨幹と骨端を隔てる軟骨層に過度な牽引ストレスがかかり続けると、骨端部の成長が阻害され、徐々に痛みや変形などの症状が現れることがあります。骨端軟骨は子どもの成長にとても重要な役割を果たしているため、骨端部の成長が阻害されることは子どもの身体にとって非常に重要な問題となります。
症状の現れ方は?

オスグッドの症状が現れる脛骨粗面の周辺の構造には、大腿四頭筋が膝のお皿(膝蓋骨)を経由して脛骨粗面に付着しています。膝関節を伸ばす際に、太ももの前側に位置する大腿四頭筋を使用します。
症状の現れ方としては、スポーツをしている学生では運動時や運動後に痛みが生じることが多いです。痛みが出ると、膝の数センチ下にある脛骨粗面が突出することがあります。 運動をしていない子どもでも、成長が著しい時期には膝への圧迫や正座などで脛骨粗面に伸張・圧迫ストレスをかけることにより、痛みや違和感が現れることがありますが、その場合でも運動ができないほどではないことが多いです。
その他の原因は?

オスグッドは、成長期の男子に多く見られる疾患ですが、サッカーやバスケットボールなどをしている子どもであれば、女子にも多く見られるスポーツ疾患です。
サッカーの競技中や練習での過度なシュートやキック、陸上競技でのストップ&ダッシュ、バスケットボールやバレーボールでのジャンプ練習などの動きが原因となりやすいとされています。このような動きの原因となるのは、大腿四頭筋という太ももの筋肉の伸縮や酷使、そして同じ動作を繰り返すことです。学生の時期は、体力や筋肉量が十分でないことも多いため、身体が不完全な状態で同じ筋肉にずっと負荷をかけることで、それを支える膝に痛みが生じてしまいます。
膝に痛みを感じ始めた場合は、しばらくスポーツを控えて、安静に過ごすことが第一です。
オスグッドを放置するとどうなる?

膝の痛みを残したまま放置したり、ケアを怠ったりすると、徐々に痛みが強くなることがあります。重症化すると、日常生活や安静時にも痛みが現れ始め、生活に支障をきたすことがあります。
また、オスグッドを放置しておくと、成長に悪影響を及ぼす可能性もあります。成長ホルモンは就寝中や運動時に多く分泌されますが、オスグッドによって痛みがあるために十分な運動ができなくなり、その結果、成長ホルモンの分泌が不十分になり、骨の成長に悪影響を与えることがあります。
成長期を過ぎると、成長骨端線は閉じ、骨は伸びなくなり、大人の骨と同様に硬くなります。オスグッドを放置してしまった結果、大人になってからも子供の時と同じような運動時・運動後の膝の痛みが再発し、オスグッド後遺症に悩まされる可能性も考えられます。
当院の施術方法について

オスグッドは運動をしている学生に多く見られる症状です。当院での施術方法としては、まず最初に指圧(マッサージ)を行い、過度な負荷がかかっている太もも周りや膝を支えているふくらはぎ周りを緩めていきます。
過度な負荷がかかっている場合、指圧だけでは十分に緩めきれないことがあります。そのような場合には、筋膜ストレッチという筋肉を覆う筋膜を伸ばす施術を合わせて行います。
ストレッチは、自分で行うと力が入ってしまったり、十分に伸ばすことができなかったりすることがあります。もし自宅でストレッチを行う際は、誰かに手伝ってもらうことが効果的です。
改善していく上でのポイント

当院に通いながら症状の軽減を目指すにあたっては、症状が出始めた初期の段階では、できるだけ頻度を多くしてご来院いただくことをおすすめしております。
その理由としては、当院では頻繁にお越しいただきながら、少しずつ刺激を加えていくという方針で施術を行っているためです。身体が完全に元の状態や筋肉の硬さに戻ってしまう前にご来院いただき、硬くなった筋肉を伸ばしたり緩めたりすることで、症状の軽減が期待できます。
また、症状が落ち着いてきましたら、ご来院の頻度を徐々に減らし、メンテナンスを目的とした施術へと移行していきます。これにより、再発予防やケガをしにくい身体づくりを目指していくことが可能です。
監修

佐倉ユーカリが丘接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:岩手県盛岡市
趣味・特技:温泉巡り、映画鑑賞、人間観察